
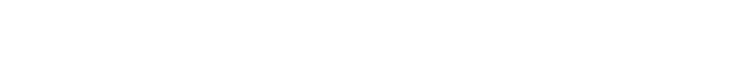
Vol.11
大岡 玲
あぶらののった金目鯛を少し厚目に切って、出汁のなかでしゃぶしゃぶと泳がせたあと、ポン酢につけて口に入れる。そのあとを追いかける豊潤な燗酒。いやもう、旨くて旨くてからだがとろけそう、なんて太平楽を述べている時には、その「ポン酢」が元は外来語だったというようなことなど、もちろんちらっとも思い浮かべない。
が、よく知られているように、「ポン酢」はオランダ語の"pons"という言葉由来だといわれている。「ポンス」はカクテルの一種なのだが、さらにさかのぼるとヒンディー語の"panch"=「五」がこの名の祖先だとのこと。五種類の液体を混ぜるカクテルが、インドからヨーロッパに伝わってできた言葉らしい。
もっとも、「ポン酢」には中国語が元になっているという少数意見もあるようで、このあたり曖昧だ。「天麩羅」とか「カステラ」、「トタン」といった語も、由来に諸説あったり、現在は元の言葉が消滅していたりするが、私たちの日常にありふれて存在する、れっきとした外来語である。
もちろん、今でも原語が存在し、意味のズレも少ない例は、ずいぶんある。ポルトガル語なら、「
また、「ピンからキリ」の「ピン」もポルトガル語由来だし、面白いところでは、「すべた」という女性に対する罵言もポルトガル・スペイン語から来たものだそうだ。トランプのスペード(エスパーダ=刀剣)の札が、カルタ(これも外来語)で悪い手になるため、エスパーダの女王札→スベタの女、なのだとのこと。こうした言葉たちは、総じて戦国期から江戸幕府初期までの百年足らずのあいだに日本に入ってきた。そして、翻訳されることなく、そのまま日本の言語に溶けこんでいったのだ。
ちゃんと訳されなかった理由は、端的に言って、これらの言葉の意味が正確にわからなくても、別段当時の日本人は困らなかったという点に尽きるだろう。ほとんどの語が具体物を指していた(キリスト教関連の語は、少々事情が異なるが)から、その照応関係を実際に知った者が音でなぞって覚えればいいだけの話であり、その「南蛮渡り」の品が普及したり、日本式に模倣されたりする過程で、名称もまた新たなものを示す新語としてそのまま受け入れられたわけである。
この点では、ある意味こんにちのコンピュータ関連機器の名称の定着と似通っているかもしれない。マウス、キーボード、プリンターetc.。三十年前には、たいていの人がお目にかかったこともなかった言葉が、今は日常語である。ただし、具体物以外のソフトやプログラミングに関するカタカナ語が、訳されないまま広く流通しているところは、多少ちがっているかもしれない。
情報弱者を決めこんでいる私などは、そうした語の意味がたいていわからないのだが、そのことに困惑しつつ、ま、どうでもいいやとあきらめている部分もある。他にも、コンプライアンスだのアカウンタビリティーだのステークホルダーだの、そういう単語を目にし耳にすると、さっぱりかっぱりよくわからんとため息をつく。そして、幕末から明治にかけて、欧米の文明・文物を必死で受け入れようと格闘した人々のことを思い浮かべ、彼らの苦労を偲ぶ気分になるのである。
あの時代の知的指導者たちは、物品だけでなく、当時の日本にはまったく馴染みのない欧米の抽象的概念を自分たち自身が理解し、それらをできる限り多くの人にわかるようにする教育的使命を負っていた。しかも、さらに厄介だったのは、語彙の意味を知り解釈をするのみならず、その指し示す事柄を日本全体に実行させねばならない、という責務もあった。そのためには、正確でわかりやすい翻訳語が必要だった。
しかし、彼らの最大の苦悩は、欧米の観念を翻訳しようにも、自分たちの言葉がそもそも統一的には存在しないという事実から生じたのだ。明治維新期の日本の言語状況は、文章語は本来は外国語である「漢文」と、漢文訓読由来の和漢混淆文、和語、それに滑稽本などに見られる俗な会話文(これも基本は和語だが)の、ダブルデッカーどころではない三層+α構造であり、口語は藩制度によって固着化が進んだ地域語・方言がどっさりあるというありさま。どの言葉をどう使ってどう訳せっていうんじゃい!
出来立てほやほやの明治政府で主導的立場を占めた多くの洋学系知的エリートたちは、こうした言文不一致を解消し、国民を啓蒙するためには、漢字と漢文からの脱却と統一的な新しい「国語」が必要だと叫んだ。郵便制度の父・前島
しかし、一方で皮肉なことに、急激な時代の要請に応える必要から、彼らは実際には次々と、欧米の言葉を見事な和製漢語へと変換していったのである。古代以来、長く漢語に抽象概念を任せていた和語では、試みてもうまく訳せなかったからだ。たとえば、西周が造語した「理性」「科学」「芸術」「技術」「主観」「客観」といった翻訳語は、私たちの現代の日本語に欠かすことができない語となっている。ほかにも、「社会」「個人」「存在」「自由」「権利」「自然」などなど、あの頃作られた単語を使えないと、それこそ私のこの文章も成り立たなくなる。
が、さらに現代においても影響が消えない深刻な皮肉は、そもそもが外国語である漢語を組み合わせて別の外国語を「翻訳」したために、その語がきわめて漠然とした広い意味を持ってしまった、いや、極論するなら意味が広すぎて無意味すれすれになってしまうケースが多く生じたことだろう。「美」とはなんぞや、とか、「社会」とは「個人」とはなんぞや、といった哲学的問いを可能にしている一端がそのことにあるのなら、これまたため息をつきたくなるわれらが言語の宿命といわざるをえないだろう。そういえば、最近氾濫するカタカナ語を日本語で言い換えようという動きがあるが、さてどうなりますか。
(この項続く)

1958年東京都生まれ。東京経済大学教授(日本文学)・作家
東京外国語大学大学院ロマンス系言語学科修了。89年『黄昏のストーム・シーディング』で三島賞、90年『表層生活』で芥川賞を受賞。書評やエッセイ、イタリア語を中心とした翻訳も手がける。近著に『本に訊け!』(光文社)、『文豪たちの釣旅』(フライの雑誌社)など。文芸誌『こころ』(平凡社)で、2013年4月から連作短篇の連載を開始。