
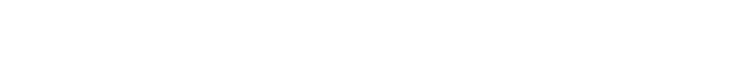
Vol.1
大岡 玲
二階建てのバスのことを、英語ではダブルデッカーと呼ぶ。deck(床)がダブルになっているからという、まことに即物的かつわかりやすい命名である。ロンドンの名物であり、ながらくイギリスの支配下にあった香港でも、現在では貴重な観光資源として活躍している。
いかにも観光客受けしそうなモノは避けて通る、という妙な俗物根性があるせいで、ロンドンや香港を何度か訪れても、ダブルデッカーに乗りそびれたまま今日に至っている私なのだが、大学新学期の日本語関連授業の準備をしていた三月某日、なぜかふいに日本語がダブルデッカーのように感じられてきた。
ん? 日本語のいったいどこが二階建てバスなのか? と、突飛な連想にとまどわれるかもしれない。しかし、日本語の歴史にある程度の知識をお持ちの方々ならば、あるいは「ははあ、あれか」と推察していただけるような気もする。
いま私が書いている文章がそもそもそうだが、日本語は漢字仮名交じり文で綴られる。漢字はいうまでもなく中国由来であり、仮名もまた独特な形で漢字を利用した
万葉仮名について、ここで詳しく述べることができるほどの学識の持ち合わせはないのでそれはやめておくが、万葉仮名的な考え方が、いかに私たちの暮らしに近しいものであるかについてはいろいろな例がすぐに思い浮かぶ。
たとえば、夏目漱石が作品に当て字(借字の一種だ)を多用したこと、いまだに「珈琲」だの「咖喱」だのといった文字を喫茶店やカレー屋の店名にすること、あるいはかつて暴走族の諸氏が「夜露死苦(よろしく)」という挨拶文字を至るところに書きなぐったことなどなど、その証左は枚挙に
これは、私たち日本人がどれほど漢字を愛しているかのまぎれもないあかしなのだが、同時にその愛の形が、「やまとことば」ともつれあいねじれあう頑固で奇妙なフォルムをなしているのも、また事実なのだ。それを、私はダブルデッカーと呼びたくなるのである。
ヤマト王朝の成立期から飛鳥・奈良朝にかけての頃、多くは朝鮮半島からの渡来人によって、あるいは遣隋使・遣唐使という直接的な交流の中でもたらされた中国大陸の文化・文明に、おそらく私たちの先祖はまばゆい光輝を感じただろう。法制度を借用し、都を唐の都を模して作り(もっとも、わが国にはかの地のような対騎馬民族用の城壁は不要だったが)、公用文書は一所懸命修得した漢文で綴られた。
私が生業としてたずさわる文学の分野にしても、現存する最古の漢詩集『懐風藻』が撰されたのは八世紀の半ば。収められた詩には、七世紀半ばの近江朝の歴史を彩った大津皇子や大友皇子といった皇族の詩もある。
もちろん、模倣というか、あきらかに類似した作風の詩が中国本土に見られたり(謀反の疑いで刑死した大津皇子の作とされる「臨終」が、その代表)、技巧的に稚拙なものも散見される。しかし、中国本土の文明に参加しようとする強い熱意が、集全体からひしひしと伝わってくるのだ。
乱暴な言い方をするなら、ヤマト王朝初期の宮廷には、バイリンガル気分が横溢していたということになるだろうか。英語グローバリズムに席巻されている現在の状況に引き写すなら、官庁の書類はすべて英語。憲法や刑法・民法も英語で、作家や詩人は競って英語小説や英詩を書くというような状態。なんだかちょっとわびしい風景のような気もするが、そんな様子を想像してみると、なんとなく当時の「熱狂」が伝わってはこないだろうか。
しかし、そうした外来文明への熱狂の中で、同時にわれらのご先祖さまは、「やまとことば」を漢字で表現するという難事に、果敢に挑戦していたのである。それはつまり、着々と母語の二重構造化に邁進していたということを意味するのである。
一つの文字で、ちゃんとした意味を担う語になる「表語文字」・漢字を使い、その意味にはこだわらずに「やまとことば」の音節をあらわしてしまうという万葉仮名という荒業。これがあったからこそ、それまでは口承でしか伝えられなかった「歴史」や伝説が『古事記』になって結晶し、あるいは万葉仮名の名の由来である『万葉集』という形で、人々の祭りに息づいていた古代歌謡「歌垣」の魂を和歌によって記し得たのである。
中華文化の仲介者であるお隣の朝鮮半島でも、同様の試みはなされている。新羅時代の歌謡である郷歌を筆記するのに使用された「郷札」や、行政文書用だったらしい「
圧倒的な中国文明への憧れと、自国の土着文化への粘り強い固執が、日本語には刻まれている。その消息を、ここで追いかけてみたいと考えている。
(この項続く)

1958年東京都生まれ。東京経済大学教授(日本文学)・作家
東京外国語大学大学院ロマンス系言語学科修了。89年『黄昏のストーム・シーディング』で三島賞、90年『表層生活』で芥川賞を受賞。書評やエッセイ、イタリア語を中心とした翻訳も手がける。近著に『本に訊け!』(光文社)、『文豪たちの釣旅』(フライの雑誌社)など。文芸誌『こころ』(平凡社)で、2013年4月から連作短篇の連載を開始。